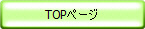
ご 挨 拶
鳥取大学附属図書館には、本学教育地域科学部の前身である旧師範学校郷土室所蔵の郷土資料が伝えられている。
戦中・戦後の混乱を経て、その後に付け加えられた史料とともに現在にいたっている。ここには、18~19世紀を主と
する近世・近代の郷土資料が豊富に集められている。
また、本学農学部の前身である旧鳥取高等農業学校が収集した農学関係の和装本を中心とした貴重資料が多く
伝わっている。
図書館では、これらの貴重資料・郷土資料の目録のデータベースを作成するとともに、主なものについては
資料そのものの画像データベースを作成し、インターネットを通して学内外に常時公開することとした。鳥取に
関する地域研究の一助になれば幸いである。
なお、このデータベース作成については、昭和10年に刊行された鳥取県師範学校『郷土研究施設要覧』、また、
特に郷土資料の分類および解説については、昭和63年に刊行された『鳥取大学所蔵文化財整理簡報』(平勢隆郎執筆)
及びその調査の際に作成された整理カードを参考にさせて頂いた。ここに厚く御礼申し上げる次第である。
平成13年10月
附属図書館長
高 阪 一 治
資 料 概 説
1.書画、短冊等
1 鳥取藩主池田家関係書画
2 儒学者の著作と書画
3 国学者、歌人の著作と書
4 俳人の著作と筆跡
5 書家の書
6 画家の絵画
7 話題性のある郷土人の書
8 郷土版元関係
鳥取池田藩主とその一族の手になるものである。為政者として文化政策を遂行する一方、 自らも範を示した者たちの事績をしのぶ具体的史料である。
1、第3代藩主吉泰(1700-39年在位)の手簡 (NO.1)
2、第6代藩主治道(1783-98年在位)の和歌の短冊と色紙 (NO.2)
3、治道の子である池田道一の書 (NO.3)
道一は文武を好み和歌をたしなんだことが、『鳥取藩史』(昭和44年鳥取県立鳥取図書館発行、151頁)にみえる。
4、第10代藩主慶行(1841-48年在位)の絵画 (NO.4) と書 (NO.5)
『鳥取藩史』(88-92頁)によれば、公は政事文武の余をもって画を学び、 狩野流を主とし沖探容を師とした。侍臣は公の賜う所の画を表装し、 公に供してこれを礼賛したという。 本絵画には、「丙午初夏」とあるが、同書によれば、 この年(1846年)4月22江戸を出発し、5月18日に鳥取に着いている。 題材が馬であるが、これも同書によれぱ、公は馬を好み、 良馬を養い馬術を善くしたというから、鳥取到着後に、 愛馬の一つを画いたものであろう。 時に14才になったばかりであった。 公は数え歳17(16才)で逝去している。
5、支藩格である西館の第5代当主たる定常(冠山、1773-1801年当主、1833年逝去)の書 (NO.6)
冠山自らが当時名の知れた学者であり、『池田氏家譜集成』等多数の著書がある。 江戸の林述斎に学び、佐藤一斎等と親交があった(『鳥取藩史』178-782頁)。 公の存在が、以後の鳥取における文化振興に与えた影響は大なるものがある。
池田冠山の著作には、『周易管窺』4巻があるが、 その他にも、本県には『周易』を研究する漢学者が相次いであらわれた。 その著作が本資料中に含まれる。 また、それらの著者の一人である伊藤宜堂の絵画が一点含まれる。
1、河田孝成(東岡、1714-92年)の著書
孝成の著書として、『周易新疏』(8巻4冊、別録2巻4冊)がある。
孝成は、若い頃三宅尚斎に朱子の易を学び、その後伊藤東涯に私淑し、荻生徂来の説に敬服した。
しかし東涯が程伊川の道義的解釈、徂来が朱子のト筮観を踏襲しているのにあきたらず、
周易をもって治道の下範、生民の道を教えるものとし、1762年に『周易雋註』10巻をまとめた。
『周易新疏』は、これを細かく分けて説明したものである。
1784年(天明4)に刊行され、1767年(寛政9)に改訂版が出された。
『和漢書画集覧』に、孝成は当時易学檀の6大家と称された
(以上『鳥取藩史』337-342頁、まとめの文章は『鳥取県大百科』417頁)。
『周易雋註』は残念ながら所蔵していないが、『周易新疏』は、寛政9年改訂版がある。
また、天明4年刊本も図書館の蔵書中に見られる。
同書の端本(巻2・3・4・5・8刊年不詳)も同蔵書中に見られる。
本資料中には、孝成の著書として、他に『孫子解』(上下2冊)もある。
また、図書館蔵書中に『司馬法解』(2冊、写本)がある。
2、土肥貫雅(鹿鳴、1745-1816年)の『周易』関係の著書
貫雅には、『周易』関係の著書が多い。そのため世に学名高く、『先哲叢談後編』には、
上記の河田孝成の他、新井白蛾・真勢中州らとともに易学大家中に人れられている
(『鳥取藩史』462-463頁)。
本資料中に、『周易卦主論』(1冊)・『周易卦変談』(1冊)・『易会要目略図解』(1冊)・『授与占言』
(上中下3冊)があるが、すべて写本にして人手困難な貴重本である。
版本としても『易学手引草』(1794年<寛政6>刊、1冊)がふくまれる。
また、『易象発揮』(8巻4冊、写本〉が、図書館蔵書中に見られる。
3、伊藤宜堂(俊蔵、1792-1874年)の著書と絵画
宜堂は本県日野郡江尾に生まれた。
江戸の朝川喜庵・佐藤一斎に学び、石州大森・太田で講学、1835年出雲市郊外の上塩谷村で有隣塾を開く。
1862年鳥取藩に招かれ、周易を講じた。
一方足羽氏の尽力で開かれた溝口郷校で、
教育にあたった。
宜堂の著書として、『周易包蒙』50巻がある。
しかし、この本は出版されるにいたらず、その写本が東北大学に所蔵されている
(『東北大学所蔵和漢書古典分類目録・和書上』328頁)のを知るのみである。
ただこの『周易包蒙』の精髄はまとめられて、
『周易包蒙約解』・『周易包蒙別録』として出版された。
この版本(両書をそれぞれ乾坤とするセット、文久2年<1862>官許)が、
本資料中におさめられている。
宜堂は、書画にもたくみであった。
彼の水墨画 (NO.12) が、本資料中に含まれる。
本史料中には、上記以外にも、本藩の儒学者による著作があり、 しかも、その著者の手になる書も収められている。
1、渓百年(世尊、1754-1831年)の書(NO.8)と『経典餘師』
渓百年は、もと讃岐の人で、寛政年間に鳥取に来た。
水戸の徳川光國の学門を慕い、『天朝史鑑』・『天朝史略』等の著書もあるというが、
かれの著作として有名なのは、江戸時代のベストセラーとなった『経典餘師』である。
天明6年(1786)の四書(『大学』・『中庸』・『論語』・『孟子』)の刊行を始めとして、
『孝経』・『小学』・『四書序之部』・『詩経』・『孫子』・『易経』・『書経』・『近思録』・『弟子職』などが、
続々と刊行された。中でも『孝経』は大変な売れ行きで、
江戸時代の間に11種類もの版本と4種類の後印本とがある(『鳥取藩史』448-454頁、『鳥取県大百科』279・559頁)。
本資料中にも、この『経典餘師』があり、四書(天保13年<1842>刊、
4刻、国漢<4>漢学15-1~10)の他、『小学』(寛政3年<1791>刊を、
文久3年<1863>再版、国漢<4>漢学15-11~15)・『詩経』(寛政5年<
1793>刊、国漢<4>漢学15-16~23)が含まれる。
また、図書館蔵書中にも、同書がある。うちわけは、
『小学』(5冊、寛政3年<1791>刊)・『詩経』(8冊、寛政5年<1792>刊・嘉永2年<1849>刊)・
『蒙求』(3冊、文政9年<1826>)・『易経』(7冊、文政2年<1819>)・『近思録』(5冊、天保14年<
1843>刊)・四書(10冊、嘉永5年<1852>刊:端本5冊、安政4年<1857>序)・
『書経』(6冊、刊年不詳:端本5冊、刊年不詳)である。
2、伊良子大洲(憲、字は子成、1763-1829年)の書と『大洲集』
「(NO.9)」は、伊良子大洲の書である。
安藤箕山(学統不明、『鳥取藩史』234-239頁、『鳥取県大百科』35頁)に学ぶ。
宋学をてがけ、直接経書について学ぶことを主張する点は、
伊藤仁斎の古学や、荻生徂来の古文辞学に近い学風をもつ。
彼は、その師の安藤箕山の遺著『仁説』1巻を出版したが、彼の著作は、
弟子の柴田温が『大洲集』15巻等を出版している(『鳥取藩史』247-252頁、『鳥取県大百科』72頁)。
本資料中に、端本ながら『大洲集』(巻8・9の一冊、刊年未詳、歴史<1>郷土史13)・
『大洲四十六士論』(版本、文政3年<1820>跋、歴史<1>郷土史13)がある。
3、柴田温(恭甫、1792-1853年)の筆跡
「(NO.10)」は、 柴田温の筆跡である。稲雨の絵に題したものである。 柴田温は、伊良子大洲の遺著(上掲)を出版するだけでなく、 自らも『性善筆話』等の著書がある(『鳥取藩史』402-404頁)。
4、正墻適処(薫、朝華、1818-75年)とその門弟の書および適処の詩集『研志堂詩抄』
「(NO.13)」は、正墻適処の書であり、「NO.14-18」は、その門弟の書である。
正墻適処は、鳥取の建部撲斎・大阪の藤沢東畩・江戸の佐藤一斎に学んだ。
子弟の教育に携わる一方、詩画に巧みで詩集『研志堂詩抄』を出し、
筆跡も優雅風韵に富むと評価される(『鳥取藩史』406-416頁)。
本資料中に『研志堂詩抄』(上下)2セツトが含まれる。
これらのうち1セットは、明治32年に倉吉の徳岡書店が出版したもので、
もう1セットは、同じ版木を使用しながら、前者よりは古い版本のようである。
いずれも貴重な郷土出版物の一つといえよう。
門弟中、山内篤処(「(NO.14) (NO.15) NO.16」)が有名である。
5、湯本文彦の書と『平安通史』
「(NO.20) (NO.21)」は、 湯本文彦(1843-1921年)の書・筆跡である。 彼は、大著『平安通史』の編者として有名であり『鳥取藩史』も彼の編著である。 本資料中に『平安通史』が合まれ、また復刻版も、図書館蔵書中にある。
6、広谷庚斎の書画とその遺稿
広谷由之(字は子和、号は庚斎、?-1916年)は、藩儒坂田順蔵・伊藤玄章に経史を学び、鳥取中学の助教となった。 後に、春日潜庵・池田草庵・東沢潟に師事し、陽明学を究めた(遺稿序文)。 後育英中学で教鞭をとる。「NO.22・NO.23」は、その書画である。 弟市蔵が、その遺稿集(「国漢<1>漢詩14」)を発刊している。
国学者・歌人の書およびその著作がある。2に同じくこれらも評価されなければならない。 伊勢の人で鳥取に来聘した衣川長秋とその門弟たちの作品が特に注目される。
1、国本道男の書画(「(NO.29)」)
道男(1774-1830年)は、 八頭郡河原町佐貫の都波只知上神社の社家に生まれ、 早くから古学に励んだ。国学振興のために、京都から伊勢の人衣川長秋の招聘を実現した。 『皇国明弁』等の著書がある(『鳥取藩史』360-362頁)。
2、衣川長秋の書(和歌懐紙、「(NO.30)」)とその著作
長秋(1766-1823年)は、伊勢の人で、本居宣長について国学を修めた。
国学振興のため、国本道男に請われて鳥取に来り、藩主斉邦公の命により国学を講じた。
また歌道をも伝授したことから、本藩の歌道はおおいに広まった。
その門下に見安父子・飯田秀雄一家・臼井治堅・加須屋武義・米原豊秋・佐治景嶺・小林大茂・中島宜門等が輩出した(『鳥取藩史』358-360頁)。
長秋の著書として、藩内の紀行文『田蓑の日記』(文政5年九月刊、「国漢<5>文学1)
・『やつれみのの日記』(文政6年正月刊の写本、「国漢<5>文学2」)が、本資料中に含まれる。
遺稿歌集『百人一首峰梯』(版本、上下2冊角部、文化12年刊、国漢<
2>和歌等33一<1・2>)や、その養子である広滋の書(「
(NO.31) (NO.32)」〉もある。
飯田秀雄は、国学を本居大平に、また歌道を加納諸平に学んだ。 著述に『樟斎漫筆』等がある。飯田年平は、その第2子、原田輝子は、さらにその妹である。 秀雄の長子秀臣の子、秀仲(『鳥取藩史』257-258頁)の筆跡(「 (NO.36)」)もある。
3、原田永寛の書「(NO.34)」とその歌集『墨園集』
永寛(墨園、帯霞、1807-71年)は、 蘭医である。因伯の地に種痘術をもたらした人物として有名である。 和歌にもたくみで、歌集『墨園集』がある(『鳥取県大百科』812頁)。 本資料中にこれ(明治18年刊、「国漢<2>和歌等61」)がある。
4、飯田年平の筆跡(「(NO.66)」)と歌集『飯田年平詠草』
年平(石園、1820-1886年)は秀雄の次 男で、父と同じく国学を本居大平に、また歌道を加納諸平に学んだ。 国学・歌道いずれの方面でもめざましい活躍をした(『鳥取藩史』258-2頁)。 彼の筆跡として、画家永眠保友の絵画に題した作品がある(「NO.66」)。 その多くの著作のうち、歌集『飯田年平詠草』の写本(「国漢<2>和歌等 22)が本資料中に含まれる。
5、原田輝子の書(「 (NO.35)」)と飯田俊子の歌集『飯田俊子歌集』・『松原としこ詠草』
輝子(1836-94年)は、秀雄の娘で、俊子の妹である。 輝子の歌集は、残念ながら本資料中に含まれないが、俊子の歌集『飯田俊子歌集』(「国漢<2>和歌等28)・『松原としこ詠草』(「国漢 <2>和歌等42)が含まれる。
6、中島宜門の書・筆跡(「(NO.37)・ (NO.38)・(NO.39)」)とその編著『類題稲葉集』
衣川長秋の門弟である宜門(1807-94年)は、藩内歌道の振興を志して、 『類題稲葉集』を編した(『鳥取藩史』471-473頁)。 これ(嘉永5年12月刊、上下2冊、「国漢<2>和歌等36-1・2」)が、 本資料中に含まれる。彼は、また尚徳館編集係として、『伯耆誌』の編纂にも関わった。 この『伯耆誌』は、図書館蔵書中に、写本(4冊)と因伯叢書版(5冊、大正5年刊)が保管される。
7、加須屋武義の筆跡(「(NO.17)」)
武義(鈴蔵・平允・松の屋・松斎・松亭、 1793-1865年)も、衣川長秋に国学を受けて、歌を善くした(『鳥取藩史』323-324頁)。 「NO.17」は、漢学者正墻適処の門人との合作である。
8、小林大茂の歌集『松屋集』
大茂(1796-1870年)は国典を衣川長秋に、 漢籍を伊良子憲に学び医方・天文にも造詣があった(『鳥取藩史』373-375頁)。 その歌集『松屋集』(国漢<2>和歌等31<明治26年2月刊>・ 32<明治27年5月刊>)が、本資料中に含まれる。
9、新貞老の著書『柿垣詠草抜粋傍註』・『大瞋道人草稿』
貞老(五郎、1827-99年)は、加納諸平に学んだ。 晩年宇倍神社宮司となり、歌道振興に没頭した(『鳥取県大百科』22頁)。 『柿垣詠草抜粋傍註』(明治30年刊、国漢<2>和歌等43)・『大瞋道人草稿』 (明治30年刊、国漢<2>和歌等44)が、本資料中に含まれる。
10、安木弘蔭の書(「(NO.40)」)とその歌集『仙動木園遺稿』
弘蔭(仙動木園、1872-1917年)は、中島宜門・新貞老に学んだ。 母は、万葉歌人大田垣知足の二女であったため、その影響を受け、純然たる万葉派として重きをなした。 その歌集『仙動木園遺稿』(昭和8年識語、国漢<2>和歌等35)・ 『不二百首』(明治44年刊、国漢<2>和歌等11)が、本資料中に含まれる。
11、香川景樹の著作
大局的に見た場合に、
我が藩の歌檀が柿園派を主流とするのに対し、独自の派(桂園派)を創始し、
全国に名をはせたのが、香川景樹(1768-1843年)である。
家集『桂園一枝』(版本、雪・月・花3冊、
文政6年刊、国漢<2>和歌等5-1・2・3)の他、
『またぬ青葉』(版本、天保3年刊、国漢<2>和歌等3)
『う寿ご保里』(版本、天保5年刊、国漢<2>和歌等4)
『六十四番歌結』(版本、嘉永2年刊、国漢<2>和歌等6)
『桂園一枝拾遺』(版本、上下2冊、嘉永3年刊、国漢<2>和歌等7-1・2)
『百首異見』(版本、5冊、嘉永3年刊、国漢<2>和歌等8-1~5)
『古今和歌集正義』(写本、4冊、国漢<2>和歌等9-1~4)
『桂の落葉』(版本、天保14年刊、2冊、国漢<2>和歌等13-1・2)
『桂園大人社中詠草奥書』(写本、2冊、国漢<2>和歌等14-X-1・2)
『新学異見』(版本、同一2部、文化12年刊、国漢<2>和歌等30-x一1・2)
『中そらの日記』(版本、同一2部、文政2年刊、国漢<5>文学3-X-1・2)
『我妻日記』(版本、文政2年刊、国漢<5>文学4)が、本資料中に含まれる。
佐々木信綱の『香川景樹翁全集』(洋装、続日本歌学全書第四編、上下2冊、国漢<2>和歌等10-1・2)もある。
1、岡西惟中の著作
惟中(1639-1711年)は、
大阪の西山宗因の下で談林派俳諧を学び、同派の論客として活曜した。
同派の衰微とともに文学研究に関心がうつり、この方面での著作をものしている。
本資料には、
『続無名抄』(上下2巻、延宝8年<1780>刊、国漢<5>文学19-1・2)
『つれづれ直解』(10冊<上巻5冊、下巻4冊、「寂莫草」の題で「一部諸系図並器物之図」1冊>
『徒然草直解』貞享三年刊の別本、国漢<5>文学20-1~10)
『消閑雑記』(『続無名抄』改題本。乾坤2冊、文政8年刊、国漢<5>文学21-1・2)がある。
このうち『続無名抄』・『つれづれ直解』は、本資料版本中、最も古い部類に属する。
2、安藤蘭鳥の還暦祝賀句集
蘭鳥(吉右衛門、武定、1708-71)は、 河村郡の大庄屋をつとめた。同郡久原の出身。 作州勝山の景山青千に俳諧を学び、近隣諸国の俳人とも交流した。 還暦(明和5年<1768>)の祝いに諸国から寄せられた祝ををまとめて、 1冊とし『俳諧豊鋤田』と題して刊行した。これは、本県最初の俳書刊行である(『鳥取県大百科』36頁)。 本資料中にこの刊本が含まれる(「国漢<3>俳句等6)。
3、俳諧歌仙軸物(「(NO.43)」)
明治三年、梅亭で挙行された俳諧歌仙である。 芭蕉の句に始まり、計36人の句を連ねる。俳諧の作法を具体的に示す貴重な資料である。 執筆に当たった釈鳳鳴(1814-78)は、鳥取覚応寺の僧である。
4、筒井寸風の筆跡(「(NO.44)」)とその遺稿
寸風(1783-1868年)は 、鳥取吉岡の人。活躍の時期は、天保年間(1830-44)に始まり、嘉永安政(1848-60)にいたって、 最高潮に達したらしい(荻原直正『鳥取俳人史』76-96頁)。 本資料中に『俳人寸風遺稿』(写本、「国漢<3>俳句等2)がある。 「短冊」中にも、彼の筆跡がある。
5、村上碩水・春月夫妻の合作書画(「(NO.45)」)
春月の絵画に碩水が題したものである。碩水は鳥取本町の産で、鳥取においては、 主として嘉永年間(1848-54)に活躍している(『鳥取俳人史』101-108頁)。 春月が絵画にたくみであったことは、現在あまり知られていない。
1、明石善之の書・筆跡(「(NO.47)・(NO. 48)・(NO.50)」)
(善之、1788-1871年)は、建部樸斎・堀靜軒に学び、詩や書に巧みであった。一方匹田流槍術をよくし、その師範でもあった。
2、児玉玉立の書(「(NO.51)」)
(玉立、子蔵、大輔、1794-1861年)は、米子生まれで、御来屋玉立とも称した。独学で書家となる。 唐の懐素に私淑し、極めて速い運筆による狂草体を得意とした。
3、田村復斎の書(「(NO.52)」)
復斎(弘、伯毅、平四郎、甚左衛門、貞彦、 1802-75年)藩医村上潜竜の子。40年藩主5代に仕え、藩政改革に尽力した。 書を建部樸斎に学ぶ。父潜竜の筆跡も本資料中に含まれる。
4、牧野芝石の書(「(NO.53)」)と絵画(額)
芝石(順造、1840-1903年)は、 画家としても著名で、本資料中、額として彼の作品がある。 書は唐様を学び、六朝風をよくす。
5、河村竹渓(正憲)の書(「(NO.54)・ (NO.55)」)
画家河村芳舟の兄。
(狩野派の画家)
1、永眠保友の絵画・飯田年平の筆跡(「(NO.66)」)
森岡保友(1802-58年)は、鳥取生まれ。京都狩野長常の助手。
2、森岡梁海の絵画(「(NO.67)」)
梁海は、永眠保友の門弟。およそ安政年間(1854-60年)頃の人。
3、根本幽蛾・橋本秀峰・大岸孤峰・梅翁・文珪の絵画合作(「(NO.68)」)
幽蛾(1824-66年)は、藩絵師。鳥取生まれ。藩絵師沖一蛾に学ぶ。
橋本秀峰は、後掲。幽蛾以下、鳥取狩野派の交流を知る上での貴重な資料である。
4、狩野幽蛾・河田樗峰・保光・袖山の絵画合作(「(NO.69)」)
河田樗峰は、後掲。鳥取狩野派の交流を知る上での貴重な史料である。
5、河田樗峰の絵画(「(NO.70)」)
樗峰は、根本幽蛾の門弟。明治初年の人。
6、河田翠涯の絵画(「(NO.71)」)
翠涯(1831-1900年)は、根本幽蛾の門弟。
秀峰(1796-1883年)は、藩士林淇園の第2子。橋本喜内の養子。江戸の鍛冶橋狩野探淵守真に学ぶ。
8、孤峰の扇面(「(NO.75)」)
9、森本成卿の絵画(「(NO.79)」)
成卿(1848-1905年)は、藩絵師沖九皐の門弟。
10、河村芳舟(鶴嶼)の絵画(「(NO.80)」)
芳舟(1879-1963年)は、鳥取生まれ。江戸狩野派の橋本雅邦の門弟。「鶴嶼」は、若い時の号。
(土方稲嶺とその一派)
11、土方稲嶺の絵画(「(NO.81)」)
稲嶺(1741-1807年)は、藩絵師。江戸の宋紫石の門下。
12、黒田稲皐の絵画(「(NO.82)」)
稲皐(1787-1846年)は、土方稲嶺の門弟。
13、住山稲僊の絵画(「(NO.83)」)
14、土方稲林の絵画(「(NO.84)」)
稲林は、稲嶺の子。本資料中には稲嶺の孫、稲洋の画もある。
15、稲雨の絵画(「(NO.10)」)
(その他)
図南(-1859年)は、鳥取生まれ。柴田義重に学び、四条派の絵をよくし、人物画にては、並ぶ者がなかったという。
17、片山楊谷の絵画(「(NO.87)」
楊谷(1760-1801年)は、長崎生まれ。鳥取に来て、 茶道家片山宗把の家を継ぐ。画系は長崎派。作品を京都光格上皇に献上し、従五位に叙せらる。 ただし当絵画については、真偽を検討中。
18、国谷春岱の絵画(「(NO.88)」
春岱は、伯州富永の人。京都の呉春・景文の門下にして四条派を極む。
19、稲岡天真の絵画(「(NO.89)」
天真は、南画文人派の人。嘉永・安政(1848-60年)頃の人。
20、藤原神山の絵画(「(NO.90)」
1、夏目漱石『坊ちゃん』に出てくる「漢学者の先生」のモデル--橋本栗渓の書(「 (NO.26(1))」
栗渓(1864-1953年)は、 漢学者にして山口高等商業学校の教授であった。 その書は雄渾である。東京帝大文科古典講習科漢書課卒業。 愛媛県尋常中学に勤務の折、同僚の夏目漱石と親しくしており、 『坊ちゃん』の一節に出る「漢学者の先生」とは、彼のことだと言われている(『鳥取県大百科』798頁)。
2、大老井伊直弼の人生の師--仙英禅師の書(「(NO.56)」)
岩美郡岩美町生まれ。 倉吉吉祥院・鳥取景福寺から彦根の清涼寺に移り、 井伊直弼に厚い信頼を受けた。
3、乃木将軍に禅を教えた禅僧--中原鄧州(「(NO.58)」)
兵庫県海清寺住職(鳥取西高『校史資料目録』その2,25頁)
1、鳥取書肆、竜淵堂の使用した版木
『小学読本』明治7年刊の版木が1点ある。他に調査中の版木が2点ある。
2、県内出版物
以下に本資料中からいくつかを列記する。近世・近代の県内学術出版物は、現存するものが比較的少ない。
・安藤蘭鳥の『俳諧豊鋤田』
上掲「俳人の著作と筆跡」参照。これは、本県最初の俳書の刊本(明和5年<1768>)である。
・中島宜門の『類題稲葉集』(版本、嘉永5年跋、国漢<2>和歌等36-1・2)鳥取油屋仲蔵刊
・正墻適処の『研志堂詩抄』(版本、上下2冊が2セット、うち1セットは明治32年刊、国漢<1>漢詩3-1-1・2、3-2-1・2)
明治32年刊本は倉吉の徳岡書店が出版。
これには、安政5年(1858)の跋と万延2年(1861)の識とがある。
幕末の刊本と同一の版木を使用して、再版したものであろう。
・木村正辞編『日本略史』(版本、上下2冊、明治九年刊、歴史<1>郷土史1)鳥取書肆、竜淵堂翻刻
3.農学関係貴重図書
4.その他
◆おことわり◆
最後に、資料の概説を作成するに当たっては、「鳥取大学所蔵文化財整理会報」 (昭和63年2月発行)に全面的にお世話になった。この整理会報を作成された方々は以下のとおりである。ここに場を借りて、謝意を表する次第である。
鳥取県立博物館 亀井煕人・福井淳人・小山勝之進・加藤隆昭
鳥取西高等学校 浜崎洋三
鳥 取 市 山本嘉将・森本定和・西林節子・山根文子
本 学 松尾葦江・錦織勤・住川英明・井内太郎
執 筆 平勢隆郎
