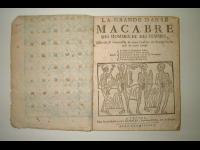エンブレム・大型コレクション
16世紀から18世紀にかけて刊行されたエンブレム(寓意図像集)関係図書全6点から成るこのコレクションは、刊行当時の西洋の世界観(思想・歴史・文学)を知る上で極めて重要な、美術的・歴史的価値の高い資料です。[サムネイル版]、[冊子体イメージ版]、[PDF版]で画像を見ることが出来ますのでご覧下さい。
エンブレムは、ギリシャ古来の西洋の伝統であるアレゴリー(寓意)を元として、中世、ルネサンス、バロックにおいて盛んに制作されました。美術や音楽、文学、演劇等の芸術全般にわたり表現上の中心的位置を占めており、その背景には、歴史観や西洋思想史上の伝統的な観念が色濃く反映されています。
このコレクションは、こうしたエンブレムをオリジナル作品から直接、研究・考察することのできる貴重な資料群です。
(この資料は平成14年度文部科学省特別図書購入費で購入しました。)
|
1. ラ・ペリエール「良き術策の劇場」 |
イタリア人アルチャーティによる「エンブレム集」(アウグスブルク版1531年、パリ版1534年)はヨーロッパ全域で大流行し、その後2,000種類以上が出版されることになるエンブレム・ブックの先駆けとなった。この影響を受けて、パリで1540年に刊行されたフランス人の手による初のエンブレム・ブックが本書である。 |
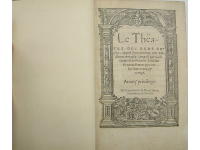
[PDF版] |
|
2. ホラポロ「ヒエログリフィカ」ギリシャ語・ラテン語版 |
タイトルの「ヒエログリフィカ」は「象形文字の秘密」という意味だが、本書は古代エジプトの象形文字について正確な知識を伝えるものではなく、古代宗教の変形としての魔術や迷信を説明したものである。そこで用いられたシンボルは、15~18世紀の芸術家や著作家たちを刺激する魅力的なものであった。エンブレム・ブックの流行を引き起こしたアルチャーティの「エンブレム集」は、この「フィエログラフィカ」を当世風にアレンジしたものである。 |
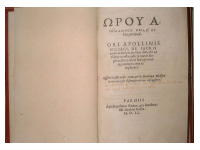
[PDF版]
|
|
3. (エンブレム)アリアス・モンタノ「人間の救済」第2版 クリストフ・プランタン印行 |
アントワープの印刷者クリストフ・プランタン(1520-1589)は、16世紀ヨーロッパの最も優れた印刷業者の一人。 |
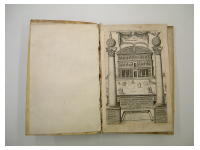
[PDF版]
|
|
4. 銅版画「死の舞踏」 |
17世紀前半のドイツの銅版画。作者不明。 マルシャンの版画を手本として流行したフランス系の「死の舞踏」に対し、15世紀半ばのバーゼルのドミニコ修道院付属墓地回廊の壁画を源流とする、ドイツ系の「死の舞踏」の存在が指摘されているが、この銅版画もその系譜に属する作品の一つといえる。 |
[画像表示] |
|
5. マルシャン「死の舞踏」 |
15世紀から16世紀のヨーロッパ全土で流行した「死の舞踏」の最初の作品は、パリのサン・ジノサン墓地回廊に1424年に描かれた壁画とされているが、パリの印刷業者ギュイヨ・マルシャンが、この壁画を手本に1485年に作成した木版画本『死の舞踏』の出版は、この図像が広範に流布する契機となった。
|
[PDF版] |
|
6. ヘンケル/シェーネ共編「エンブレマータ:16/17世紀の象徴芸術」全2巻 Henkel, Arthur & Albrecht Schöne, eds. |
ドイツ、オランダ、フランス、スペイン、イタリア、イギリスのエンブレム本に関する書誌。ゲッティンゲン・アカデミーの後援で刊行された。 |
画像はありません。 |
<参考>
アンドレア・アルチャーティ著、伊藤博明訳『エンブレム集』ありな書房、2000年
小池寿子著『「死の舞踏」への旅 : 踊る骸骨たちをたずねて』中央公論新社、2010年
著作権について
・エンブレム関係コレクション・オリジナルページの著作権は、原則として鳥取大学附属図書館に属します。
・画像の印刷やダウンロードは研究・教育を目的とした利用に限ります。